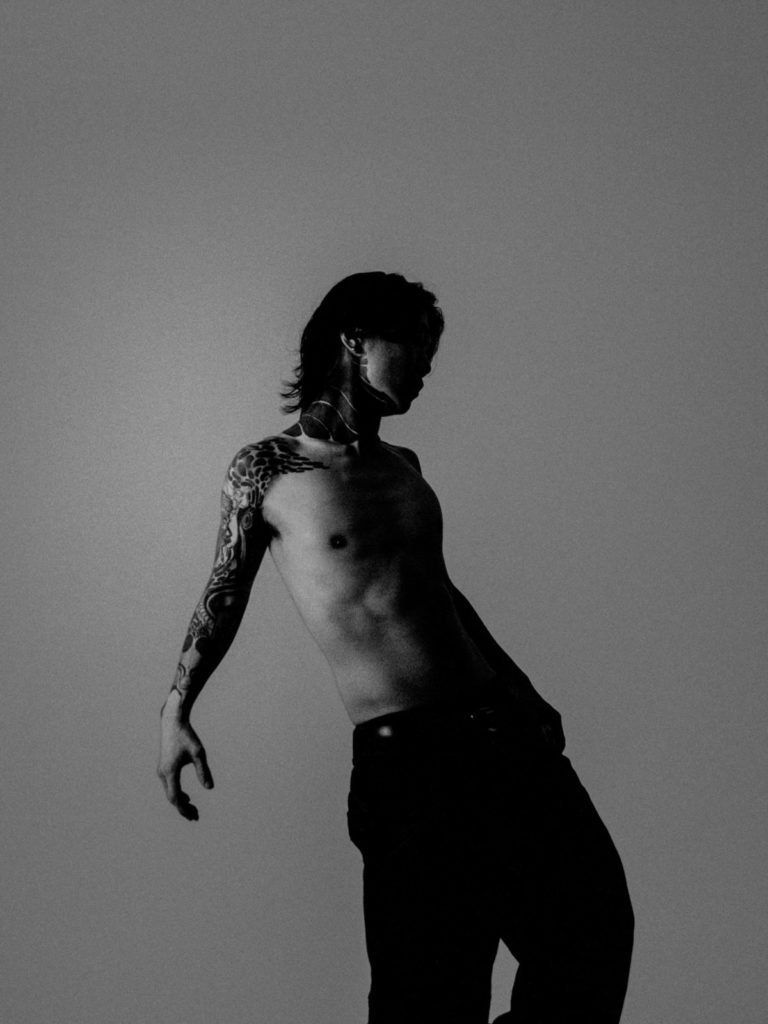G4CH4が放つ思索のビート集『Ge-stell』が映し出すものとは?
写真:JET
DJ、TYOSiNのギター、プロデューサー、ビートメーカーとして活動するG4CH4(ガチャ)が、個人名義では初となるEP『Ge-stell(ゲシュテル)』をリリースした。
サウンドだけでなく、アートワークも自身の手で手がけ、CGによるビジュアル制作を一貫して行っている。
ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーが提唱した概念である「Ge-stell(ゲシュテル)」をタイトルに冠した本作は、テクノロジーに囲まれた現代において、その構造自体を見つめ返すような、静かで鋭い問いを内包した作品となっている。
曲ごとに構造や空気感が異なる、全編インストゥルメンタルのビート集『Ge-stell(ゲシュテル)』の、制作に至るきっかけや、作品に込めた思いについてG4CH4に話を伺った。
–リリース情報–
G4CH4『Ge-stell』
配信日:2025年6月21日
配信リンク:https://linkco.re/XRQsMEbu
【収録曲】
- Arousal
- Drift
- Echo Chamber
- Mass-Aligned
- Vestige
- Passage
Cover artwork by G4CH4
ーーEP『Ge-stell』は、G4CH4(ガチャ)名義で初のリリース作品とのことですが、制作のきっかけは?
G4CH4:リリースのきっかけとして大きかったのは、ビートライブへの出演です。
clubasiaのスタッフのミドリちゃんに、ビートライブに興味があることを何気なくこぼしたら、「そういうイベントあるよ」って教えてくれて。
もともとやってみたい気持ちはあったんですけど、なかなか実行に移すタイミングがなくて。
このタイミングを逃したら、一生やらないかもしれないと思い、何も決まっていないまま「出ます!」と勢いで出演を決めました。
実際にビートライブをやってみたら、想像以上にお客さんたちがブチ上がってくれた印象があって、「じゃあもう、これはちゃんと作品として出そう」と思って、そこから急ピッチで準備を進めて、今回のリリースに至りました。
ビートメーカーなので、普段からストックというか、時間があればちょこちょこ曲を作りためたりしているので、今回のEPには、その中でも自分が気に入っているものを選りすぐって入れています。
ーー『Ge-stell』は、どのようなコンセプトやテーマが込められていますか?
G4CH4:僕は普段から「この考え方って何て言うんだろう?」とか、「どんな思想に当てはまるんだろう?」みたいに、自分がふと気になった思考や考え方を調べるのが好きで。
調べると、意外と自分の考えに近い言葉や概念が見つかることも多かったりするんですが、そんな中で、技術について色々と考えていたときに出会ったのが、「ゲシュテル(Ge-stell)」という言葉でした。
ゲシュテル(Ge-stell):哲学者のハイデガーが提唱した、近代技術が人間の存在や自然を「資源」として把握する枠組みのこと*
*参考文献:マルティン・ハイデガー『技術への問い(Die Frage nach der Technik)』(関口浩 訳、平凡社ライブラリー)
G4CH4:ゲシュテルとは、自然にある水流や地熱のような現象が、技術によって人間の目的と結びつけられることで、「使えるもの=資源」として捉えられてしまう、といった概念のことなのですが、たとえば、ただ流れているだけの水って、普通に自然の現象としてそこにあるものですよね。
でも、それを「水力発電に使える」と目的を持って捉えるようになる。
そういう変化が起きる“視点のスイッチ”が、ゲシュテルっていう考え方の出発点だったと思うんですよ。
最近だと、AIカルチャーにも個人的に関心があって調べたりしているんですが、AIの発展によって、個人の情報すら“資源”として扱われ始めているように感じていて。
技術という枠組みが巨大化していく中で、ゲシュテルが包み込む領域もまた、以前に比べて格段に広がっているように感じています。
肥大化する「Ge-stell」(ゲシュテル)が生む悲劇
G4CH4:技術の発展がすごい勢いで進む一方で、便利になったぶん、“創作の悲劇”のようなものも生まれている気がしています。
たとえば、レコードが生まれたことでコンサートや生演奏の価値が変わったり、DTMの普及によってスタジオミュージシャンのあり方が変わったり、CDよりサブスクが主流になったりと、技術の拡大によって、さまざまな時代の変化が起こってきました。
そうした変化の中で、技術が包み込む“中核”そのものも、時代とともにどんどん大きくなっている。
つまりは、ゲシュテルがどんどん拡張しているような感覚があるんです。
「ゲシュテル」という概念を知っていること自体が現代技術への心構え
G4CH4:この「ゲシュテル」という概念を知っていること自体が、これからの進化や技術の加速に対して、自分なりの姿勢を持って向き合うための心構えなんじゃないかと感じるようになりました。
今回のEPも、パソコンがなかったら、そもそも僕は作曲できないですし、EPに入っている音の中には、サブスクリプションのサンプルサイトから引っ張ってきたものもあります。
そういった“技術の枠組み”の中でできあがった作品だからこそ、この作品に「Ge-stell(ゲシュテル)」というタイトルをつけました。
ーー今回のEPは全編を通してインストゥルメンタルの作品ですが、意図などはありますか?
G4CH4:今回の目的は、ビートを聴いてもらうこと。そのため、インストゥルメンタルとしてリリースするのが自然だと感じました。
EPの中にはメロディが入っている曲もありますし、ボーカルのサンプルがループされている曲もあるのですが、それらは“歌”として聴かせたいのではなく、あくまでビートの一部、音色のひとつとして取り入れているものです。
僕自身、昔からインストのバンドも好きで、インストって各パートのフレーズが聴き取りやすいじゃないですか。そうした音の絡み合いをじっくり味わえるのが、インストならではの醍醐味だと思っています。
今回はヒップホップだけでなく、ベースミュージックやテクノ、ジューク/フットワークといったジャンルからの影響もあって、それらの音楽ではインストが前提であることも多い。そういった文脈が、自分の中にも自然と根付いているのかもしれません。
だからこそ、「インストで出す」という選択は、特別に意識したというより、ごく自然な流れだったと思います。
ーーEP全体の構成はどのように決めましたか?
G4CH4:曲の並びについては、並べてみて一番良かった順です。
「Arousal」が1曲目というのは最初から決めていました。
ーータイトルはどのように決めていくのでしょうか。
G4CH4:タイトルを考えるのにはけっこう時間がかかるので、曲を作ったあとにつけることが多いです。
曲から浮かんでくるイメージを頼りに、「しっくりくる言葉は何かな?」と探していく感じですね。
頭の中にぼんやりと“ミュージックビデオ的な映像”が浮かぶような感覚に近くて。
そこまで具体的じゃないんですけど、どういう感情かとか、空気感とか、そういうイメージから探っていきます。
ーー各楽曲について、制作時に意識したことやこだわりを教えてください。
「Arousal」
Ableton Push2というコントローラーを手に入れた直後に作った曲で、自分の中でも新しい実験をしたつもりです。Ableton Push2も触りまくりで、そのために曲を作ったみたいな感じです(笑)
意識したのは、やっぱり最初の部分ですね。長めのイントロがあって、そこに少しずつメロディが入ってきて、一度リズムが途切れたあとに、全く別の展開が始まる。その流れはかなり意識して作りました。
開放感というか、地に足がついたような静かな状態から、一気に空へと解き放たれていくようなイメージで。
「Drift」
これは、ビートライブをやるにあたって曲数が足りなかったので、急ピッチで作った1曲なんですけど、特にグルーヴ感を意識して仕上げました。全体的にそうなんですが、なかでも“頭が揺れる感じ”とか、“体が震える感じ”みたいなノリの良さが出せたらいいなと思って。そういうグルーヴが、自分はやっぱり好きなんですよね。
逆に、声の歪み方やちょっと不気味な雰囲気にもこだわっていて。ボイス素材を歪ませたり、少し切り刻んだりして加工したんですけど、その作業がすごく楽しくて印象に残ってます。
ビートライブを前提にしていたので、踊れるパートや“ここがメイン”というセクションをはっきりと作ろうと思っていました。「ここでこう来て、次にこう展開して…」と、ブロック単位で流れを意識しながら構成しています。
あと、アニメ『ベルセルク』の“蝕”の場面からサンプリングを入れていたりもします。
「Echo Chamber」
これは本当に“踊れる”ような曲を目指していて、少しインダストリアルテクノっぽい要素も意識しました。コンクリートのような、どう考えても冷たい質感のサウンドデザインというか、そういう無機質さはかなり意識的に作っています。
そのなかで、“嫌じゃないライン”を探りながら、人が踊れるようなグルーヴになるように考えていきました。
タイトルの「Echo Chamber」は、SNSで似た価値観の人ばかりをフォローしていると、情報が反響して戻ってくるような状態のことを指す言葉だと思うんですけど、その“閉鎖感”というか、“暗い雰囲気”にちょっとシンパシーを感じていて。コンセプトにも合っているし、響きとしてもしっくりきたので、そこからタイトルをつけました。
「Mass-Aligned」
この曲は、今回のEPの中でもたぶん一番古くて、かなり前に作ったものなんですけど、ボーカルのサンプルをループさせていて、断続的に同じ声がずっと流れているんです。
その“声”が、どこか整列されているような印象があって。リズムもオンタイムで、パチッ、パチッと、キレのある感じで進んでいく曲です。全体的にすごく“整った”感覚が強くて、今回のEPの中でも一番そういう方向性が出ている曲だと思います。
DTMって、1小節ごと、1拍ごとにグリッドがあるじゃないですか。
今回のEPでは、そういうグリッドからあえて外して、有機的で人為的なズレを意識した曲も多いんですけど、この曲はむしろその逆で、すごくきっちり整列されている。
声もどこか“大衆の声”みたいに聴こえてくるし、そういう意味でも、機械的で無機質な秩序みたいなものを表現しているところがあるのかなと思っています。断続的なボーカルループが、大衆の声に聞こえたことがきっかけで、「Mass-Aligned=大衆に足並みを揃えた状態」というタイトルにしました。
「Vestige」
この曲は、ビートライブでの最後の曲として「Passage」をやろうと最初から決めていたんですけど、ライブの締めにいきなり本編ラストにいくのって、ちょっと唐突すぎるかなと思ったんですよ。
それで、ラストに向かう“間”のような役割の曲を挟みたいなと思って、「Passage」の中で使われているピアノのフレーズを、あえて分解してピアノアレンジっぽく組み直して作ったのがこの曲です。
ただ、いわゆる“インタールード”みたいな扱いにはしたくなくて。曲間を繋ぐだけのものじゃなくて、ちゃんと1曲として存在していてほしかった。「Passage」が持っているあたたかさや余韻を、もう少し膨らませたようなイメージで作っています。
「Passage」
EPの締めくくりとなる曲。タイトルには「通り抜ける」などの意味があり、作品全体の“出口”のような感覚です。ビートライブでもこの曲で終えたことで、しっかりと完結感が生まれたと思っています。
あと、ちょっとした思い出なんですけど、この曲は一度、TYOSiNのイベントの時に、ライブハウスの音響で自分のビートを聴いてみたくて、勝手に流してみたことがあったんですよ。
そしたら「これ誰の曲?」って聞かれて、ViryKnot(ビリーノット)がすごく褒めてくれたんですよね。一通り全部の曲を聴かせたあとに、「さっきの曲もう一回流して」って言ってくれて、「あー、この曲いいんやな」って思って。やっぱりViryKnotに褒められるのは嬉しくて、他のみんなもいいねって言ってくれて。それが今でも印象に残ってます。
ーーG4CH4さんはDJとしても活動されていますが、DJとビートライブにはどんな違いがありますか?
G4CH4:DJって、すでに完成された曲を選んで流して、どうミックスするかで場の空気を作っていくものだと思うんですけど、ビートライブはもっと“自分が作った音”をそのまま聴かせにいく感じなんですよね。
自分にとっては、ビートライブの方が“素”というか、より自分の中から出てきたものをダイレクトに見せる行為というか。DJのときは、お客さんの空気を見ながら選曲することもあるんですけど、ビートライブは「これが俺の音です」って投げかける、もっと主観的でパーソナルな表現に近い感覚があります。
友達にM3くんっていうビートメイカーがいるんですけど、彼もビートライブをやっていて。僕がビートライブを終えた少しあとに、今度は逆にM3くんのビートライブを観に行ったんです。それがすごく良くて。
ビートライブって、その人の内面がすごく出る表現だなって感じたんですよね。さっき話したDJとの違いにも関係するんですけど、たとえばM3くんのライブを観ていても、すごく“その人っぽさ”が出ていて、自分のときもそうだったなって思って。
心の繊細な部分だったり、「自分がこれがいい」と思ってる感覚が、100%そのまま出る。それってバンドにも通じる部分があると思うんですけど、ビートライブは特にそういう“自分そのもの”が出やすいのかもしれないです。だからこそ、観ていてすごく見ごたえがあるんだと思います。
ーージャケットやビジュアルも自身で手掛けているとのことですが、どのように制作しましたか?
G4CH4:1〜2年前くらいから本格的にCGを学びはじめて、「Unreal Engine」というソフトを使って制作をしています。
今回のジャケットも、自分でCGを作ったほうがコンセプトをストレートに表現できそうだと思って、自分で手がけました。もちろん時間的な制約もあったんですが、やっぱり自分で作るほうが納得のいくものになる気がして。

ーー今回の作品のリリースを経て、心境の変化などはありましたか?
G4CH4:今回のEPは、自分にとって「この作品を出す」ということ自体が、大きな意味を持っていると思っています。
今、32歳なんですが、この年になるまで“G4CH4”名義でEPや作品を出してこなかったのは、ずっと踏み出せずにいたからなんです。
納得がいっていなかったというか、自分が本当にやりたいことがはっきりしていなかった。音楽的にも「このジャンルをやりたい」と明言できるものがなくて、どこかで「別に自分じゃなくてもいいんじゃないか」という気持ちがあったんだと思います。
でも、ビートライブを経験したことで、「自分が気持ちいいと思えるものを、人と共有したい」という気持ちの方が強くなったんです。
今回のリリースが、その思いを突き詰めていくための“助走”になればいいなと思っていますし、これからはどんどん作品を出していきたいですね。
ーーこのEPはどんな人に届けたいですか?
G4CH4:「どんな人に届けたいか」というよりは、ダサくても、かっこよくてもいいから、とにかく“感情が動く”という体験をしてくれる人に届けば嬉しいなと思っています。
それに、「これを聴いて何かを考える」とか、思考の連鎖が起きたとしたら、それこそ作品を出す意味があるんじゃないかと。
ただ音楽を発表するだけじゃなくて、聴いた人の中に“考えるきっかけ”が生まれるようなものにしたいという気持ちがありました。
もちろん、最初に曲があってEPができあがったという順番なんですが、すべてが最初からコンセプトありきで作ったわけではないので、「今からひとつの意味を通すとしたら、何があるだろう?」と考えたときに、“技術の枠組み=ゲシュテル”という概念を認識することが、自分の中でとても腑に落ちたんです。
だからそのあたりも含めて、聴いてくれた人の中に、何かしらの感情や思考が残ってくれたらいいなと思っています。
G4CH4(ガチャ) Profile
ギタリストとしてのバンド活動を通じて楽曲制作を始め、その後、ダンスミュージックとの出会いを機にDeskTop Music(DTM)での制作へと移行。
現在は、アーティストや企業への楽曲提供やミックスなど、多様な音楽制作に携わっている。TYOSiNのギタリストを務めるほか、ビートメイカー、DJ、CGデザインなど、ジャンルや形式にとらわれず活動の幅を広げている。
各種SNS情報
Inatagram:https://www.instagram.com/g4ch4_beats/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCoMhI-8od8xMUnToOh7Yh5w
Tunecore:https://linkco.re/XRQsMEbu
BUZZチケ編集部注目ポイント
テクノロジーの構造に静かに問いを投げかける、G4CH4初のソロEP『Ge-stell』。
インストビートで語る哲学、そして“作ること”への覚悟が詰まった一作。